皆さん、こんにちは。東京都世田谷区を拠点とし、注文住宅・新築工事やリフォーム・リノベーション工事を手掛ける川津工務店株式会社です。
「耐震等級3って、本当に必要なの?」「コストが高くなるだけじゃないの?」
家づくりを考えている方から、よくこんな声を耳にします。
たしかに、耐震等級3を満たすためには、設計や施工の手間も増え、費用もかかります。しかし実際の地震データを見てみると、「意味がない」と言われるどころか、家族の命と暮らしを守るための大きな違いがあることが分かります。
今回は、「耐震等級3」の本当の意味と、見落としがちな注意点、そして賢い取り入れ方を、木造建築のプロの視点から解説します。
■「耐震等級3は意味がない」と言われる理由

「耐震等級3は過剰」「標準の等級1で十分」といった意見があるのも事実です。ここでは、その理由を整理してみましょう。
・建築コストが上がってしまう
耐震等級3の家は、設計段階でより緻密な構造計算を行う必要があります。また、強度を高めるために柱や梁を太くしたり、金物の数を増やしたりと、建材や施工費が上がります。
一般的には、同規模の住宅でも耐震等級1と比べて100万〜200万円ほどコストが増えることもあります。
・間取りに制約が出やすい
耐震性を確保するためには、耐力壁や柱の配置バランスが重要になります。
そのため、「壁の少ない広々したリビング」や「大きな吹き抜け」「リビング全面の窓ガラス」などが難しくなることもあります。とはいえ、設計力の高い工務店なら、構造を工夫して耐震性と開放感を両立することが可能です。
・「建築基準法の最低基準で十分」という考え方
新築住宅は、建築基準法によって最低でも耐震等級1を満たすことが義務づけられています。このため、「法律で定められた範囲で十分」と考える方も少なくありません。しかし、等級1はあくまで「倒壊しない」ことを目的とした最低限の水準。「損傷を防ぎ、住み続けられる家」にするには、より高い等級が求められます。
・どんな家でも100%安全とは言い切れない
耐震等級3でも、地盤の弱さや繰り返す揺れによるダメージ、想定外の巨大地震までは完全に防げない可能性もあります。ただし、それでも生存率や生活の再建のしやすさが変わってきます。「100%安全ではない=意味がない」ではなく、「被害を最小限にする備え」として考えるとよいでしょう。
■そもそも「耐震等級3」とは?知っておきたい基礎知識を解説

「耐震等級3」という言葉はネットや住宅広告、モデルハウスでよく耳にしますが、
実際にどんな基準なのか、詳しく知っている人は意外と少ないのではないでしょうか。
ここでは、耐震等級3の概要と知っておくべき基礎知識を紹介します。
・耐震等級3とは?
耐震等級とは、住宅の地震に対する強さを示す国の共通指標です。
国が定める「住宅性能表示制度」(=品確法)に基づき、耐震性能は1〜3の3段階に分類されます。等級1は建築基準法で定められた最低基準に相当し、数字が大きくなるほど耐震性能が高くなります。
等級1:建築基準法の最低基準。おおむね「数百年に一度」といわれる大地震(震度6〜7)でも倒壊しないレベル。
等級2:等級1の1.25倍の強度。主に学校や病院など、人が多く集まる公共施設で採用されています。
等級3:等級1の1.5倍の強度。消防署や警察署といった防災拠点と同等の耐震性を備えた住宅です。
つまり、現行制度において耐震等級3は住宅の最高ランクの耐震性能。建築基準法を満たすだけでは得られない余裕のある構造設計で、地震後も暮らしを守ることを目的としています。
・知っておきたい基礎知識
命を守る最低ラインの建築基準法と、住み続けられる家のための品確法
ここで少し整理しておきたいのが、「建築基準法」と「品確法(住宅性能表示制度)」の違いです。どちらも国の制度ですが、目的が大きく異なります。
・建築基準法は「命を守るための最低限の基準」
建築基準法は、すべての建物が守らなければならない最低限の安全基準を定めた法律です。耐震性能でいえば、「地震時に倒壊や崩壊によって人命を損なわないこと」が目的で、命を守るための最低ラインにあたります。したがって、震度7クラスの地震で建物が損傷しても、倒壊しなければ基準法上は合格ということに。つまり、人命は守れても、家そのものは住めなくなる可能性があるということです。このように建築基準法はあくまで「命を守るための最低限の基準」として設計されているのです。
・品確法(住宅性能表示制度)は「地震後も住み続けられる家」を目指すための基準
一方の品確法(住宅性能表示制度)は、建築基準法よりも一歩踏み込み、「倒壊を防ぐ」だけでなく「損傷を減らして住み続けられる」ことを目指した制度です。
この制度では耐震性能を数値化し、等級1〜3で段階的に評価します。中でも等級3は、建築基準法(等級1)の1.5倍の強度を持つ最高ランクで、生活の継続性を確保する指標とされています。
■【データで解説】熊本地震における耐震等級3の有効性

では、本当に耐震等級3はオーバースペックで無意味な投資なのでしょうか?
その問いに明確な答えを示したのが、2016年に発生した熊本地震です。 この地震が従来と決定的に違ったのは、「震度7の揺れが2度も発生した」という点です。建築基準法が想定していたのは、「本震は1回」でした。
国土交通省の調査によると、耐震等級3で建てられた住宅は、倒壊・大破した建物がゼロでした。 それどころか、多くが無被害(87.5%)、または軽微な損傷(12.5%)で、地震後もそのまま住み続けられる状態を保っていたのです。
一方、建築基準法の最低基準である耐震等級1(現行基準)で建てられた住宅では、倒壊や大破に至ったケースが複数報告されました。
耐震等級3は、この「繰り返す大地震」に対しても有効であり、家族の命を守るだけでなく、「地震の後も住み続けられる家」、つまり家族の日常と財産を守る上で、非常に大きな意味があることを証明したのです。
つまり、耐震等級3「意味がない」どころか。大地震が頻発する日本において、その価値を最も明確に示したのが熊本地震のデータでした。
》参照:国土交通省 住宅局 - 「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」報告書のポイント
■耐震等級3のメリット・デメリット
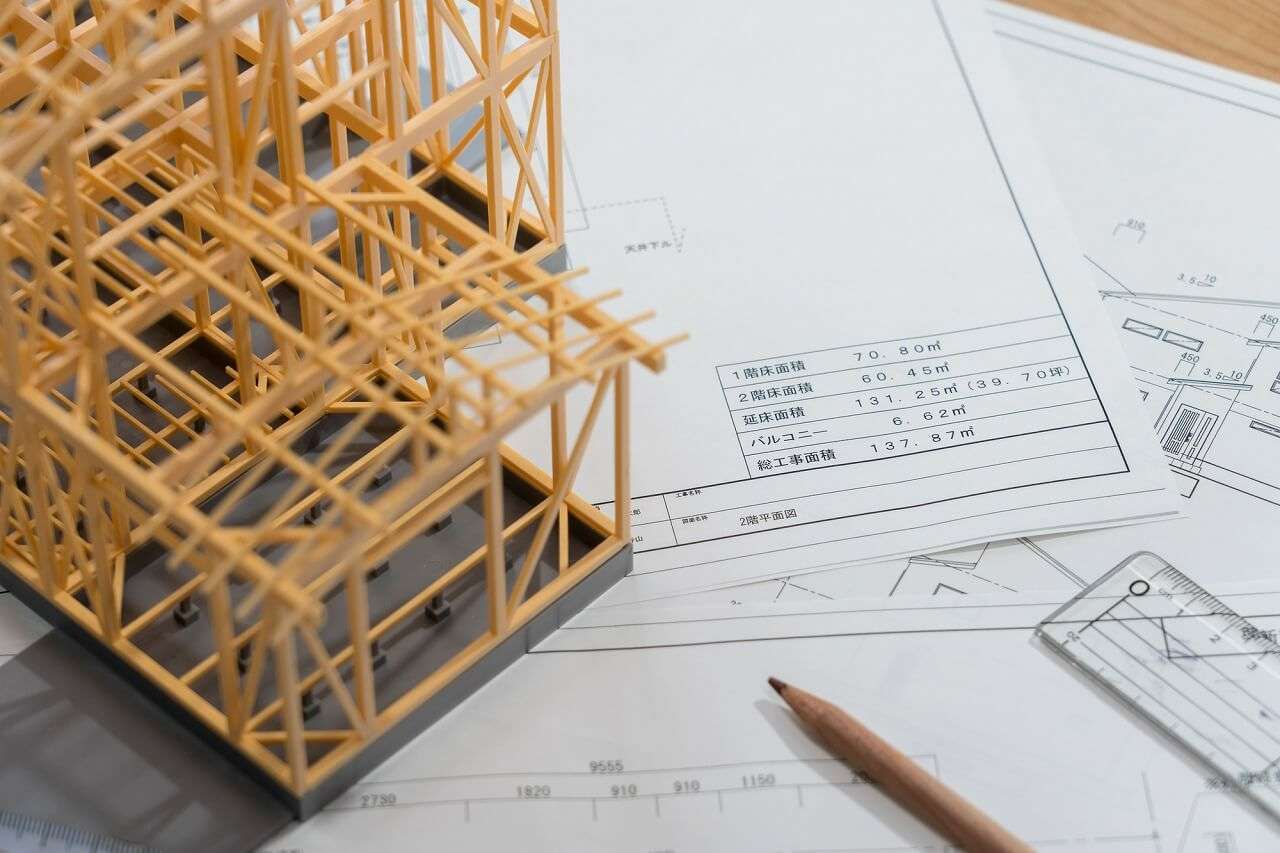
実際に耐震等級3を採用することで得られるメリットと、注意しておきたいデメリットを整理してみましょう。
・耐震等級3のメリット
最大の利点は、高い安全性と安心感です。耐震等級3の家は、大地震時の倒壊リスクを大幅に減らせるよう設計されており、繰り返しの揺れにも強い構造を備えています。
経済面でのメリットもポイント。耐震等級3の住宅は、地震保険料が最大で約50%割引になるほか、「フラット35S」などの住宅ローンで金利優遇を受けられる場合があります。
安全性が高い家は、国や金融機関からもリスクの少ない資産として評価されるため、長期的に見ても家計への負担を軽減できるのです。
さらに、こうした性能の高さは将来の資産価値の維持にもつながります。
中古市場でも、耐震性能が明確に評価できる住宅は買い手からの信頼が厚く、将来的に売却や相続を検討する際にも有利に働きます。
・耐震等級3のデメリット
前述のように、建築コストや間取りの自由度に影響が出る場合があります。
ただし、設計段階でバランスを取れば、デザイン性と耐震性の両立は十分可能です。構造とデザインの両面から提案できる工務店を選ぶことが重要です。
■その家、本当に耐震等級3?「等級3相当」との大きな違い

耐震性能の高さをアピールする住宅が増え、「耐震等級3相当」という言葉を見かけることもあります。しかし、「等級3」と「等級3相当」はまったくの別物です。
見た目の安心感だけで判断してしまうと、実際には公的な性能評価を受けていないケースもあり、保険やローンの優遇を受けられない可能性があります。
・「耐震等級3」とは?
「耐震等級3」は、国に登録された第三者機関(住宅性能評価機関)による厳正な審査を受け、正式に認定された住宅です。
図面や構造計算書をもとに耐震性能が確認されるため、客観的な証拠としての信頼性が高く、地震保険の割引や「フラット35S」などの住宅ローン金利優遇といった公的なメリットも受けられます。
・「耐震等級3相当」とは?
一方、「等級3相当」という表現は、あくまで住宅会社や設計者が自社の判断で同等レベルとみなしているだけのものです。第三者の審査を経ていないため、設計通りの耐震性能が確保されているかどうかは外部から確認できません。性能保証や公的優遇を受けられないリスクがある点に注意が必要です。
■耐震等級3だけでは不十分?性能を100%引き出すための4つの条件

とはいえ、どんなに高い等級を取得しても、完璧な安全が約束されるわけではありません。地盤・施工・構造計算なども大きく関係してきます。耐震等級3の性能を活かすために欠かせない4つのポイントを紹介します。
・制震技術の併用
耐震が地震力に「耐える」のに対し、制震は「揺れを吸収する」技術。制震ダンパーを組み合わせることで、繰り返しの地震にも強く、建物への影響を和らげます。
・地盤の強度
どんなに頑丈な家でも、地盤が弱ければ意味がありません。場合によっては地盤調査と必要な改良工事を行い、液状化などのリスクを抑えることが大切です。
◉世田谷区の地盤・液状化についてはこちらも参照してみてください
・施工精度
熊本地震では、施工不良が原因で被害を受けたケースもありました。図面通りの精度で施工することが、耐震性能を引き出す前提条件です。
・構造計算の方法
同じ「耐震等級3」でも、壁量計算よりも精密な許容応力度計算による設計のほうが信頼性は高くなります。設計段階でどの計算方式を採用しているかを確認しましょう。
■まとめ

「耐震等級3は意味ない」と言われることもありますが、実際にはまったく逆です。耐震等級3は、単に頑丈な家をつくるためではなく、大地震のあとも住み続けられる家を実現するための基準です。
熊本地震でも、耐震等級3の住宅は倒壊や大破がゼロという結果が示されています。
つまり、建築基準法の「命を守る最低ライン」を超えて、「住まいと暮らしを守る設計」こそが等級3の真価といえます。
もちろん、設計や施工の精度が伴わなければ本来の性能は発揮されません。初期コストはやや上がりますが、地震保険料の割引や資産価値の維持、家族の安全を考えれば、長期的にはコストパフォーマンスの高い選択だと言えるでしょう。
■世田谷区で「本当に安心できる耐震住宅」を建てるなら、川津工務店にお任せください

世田谷区を拠点とする川津工務店は、腕利きの大工が中心となって家づくりを行う地域密着型の工務店です。木造住宅の構造を熟知し、耐震・断熱・デザインを一体で考えたプラン提案を得意としています。
「耐震等級3は意味ない」と思われがちですが、私たちは現場で数多くの木造住宅を手掛ける中で、ちょっとした差が安心を大きく左右することを知っています。耐震等級3の認定取得はもちろん、構造計算・施工精度までをトータルで確認し、数字だけでなく実際に強い家をつくることを重視しています。
新築だけでなく、耐震補強リフォームや間取り変更、断熱改修なども対応しており、現場を熟知した自社大工が、暮らしの安全と快適さを両立させる施工を行います。
「どこまで耐震性能を上げるべきか」「予算内でできる強化策を知りたい」など、初期段階のご相談も大歓迎。地域に根ざす工務店として、「住まいの萬屋(よろずや)」のように、暮らしを支える存在でありたいと考えています。
世田谷区で地震に強く、長く安心して暮らせる家を建てたい方は、ぜひ一度川津工務店にご相談ください。
▼関連記事▼
》戸建て35坪の家は狭い?快適に暮らすためのポイントや建てる前の注意点を紹介!
》建売住宅はやめたほうがいいって本当? 注文住宅との比較でわかるメリット・デメリット
》新築でやっておけばよかったと後悔する前に!よくある失敗や、後悔しないためのポイントを紹介!
》家を建てるのにベストなタイミングは?平均年齢や知っておくべきポイントを紹介!
》3階建ての家はやめた方がいいって本当?メリットや後悔しないためのポイントを紹介!


